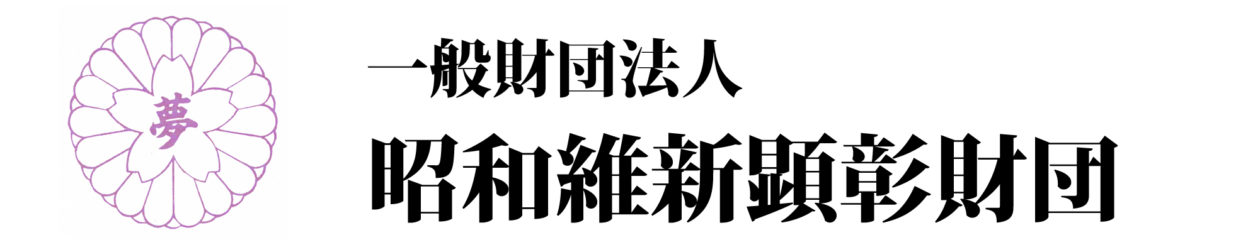令和七年元旦、大愚花房東洋が急逝いたしました。今回の「大夢舘日誌」は長男の愚元より訃報を知った元旦から一月五日に行われた葬儀までの事を愚元目線でお伝えいたします。(日誌作成・愚元)


一月一日
午前六時、妹である寿美乃から私の妻に一本の電話があり、父である花房東洋の訃報を知らされました。
悲しむ事も、涙の準備も出来ていないまま、夢の中を行くような感覚で京都まで車を走らせました。
病院で見た父の亡骸は、まるで赤子が眠っているような安らかな表情で「親父」と呼んだら目を覚ましそうにも思えました。
死因は溺死。ヒートショックによるもので、病院以外の場所で亡くなった事で、遺体は警察署に運ばれ検視を受ける事になる。
中部地方に住む兄弟家族は、岐阜にある実家大夢舘に先乗りして、お通夜、葬儀、火葬場の段取りを三男の信輔が中心となって行いました。
関西地方に住む兄弟家族は、検視が終わるまでに知人への連絡や、遺体を岐阜まで運ぶ段取りを妹の愛と寿美乃が中心となって行いました。
一月二日
夜になってようやく父が大夢舘に戻ってきました。
二階の床の間に布団を敷き父を横たえさせた時、ようやく(帰るべき場所に戻って来れたね)と安心できた気がしました。
火葬場の都合で、五日の葬儀まで二日半ほど時間が取れたため、十三人の子供や、その孫たちや、知人、友人、同友、門下の方々が最後のお別れに来て下さりました。
一月三日~四日
お通夜、葬儀では次男の兼輔があげる祝詞で見送られ、父は本望だったと思います。
棺に花を添えて、いよいよ出棺、人生を捧げた思いの深い大夢舘を後にします。
喪主である私が遺影を抱いて、父を乗せた車の助手席に乗り火葬場に向かいます。
車が走り始めてすぐに蝉時雨のような耳鳴りが鳴りはじめ、道中ずっと聞こえていました。
近親者のみと言っても子沢山の父ですから三十名ほどになりました。
炉に運ばれる瞬間、耐えていたものが弾けて「親父!」と声が出てしまい。心の中で(ごめんな、ごめんな)と繰り返し男泣きをしてしまいました。
しかし、最後の別れがこれではいけないと思い直し、最敬礼をして「ありがとうございました!」と言うと、後方からも門下の方々がそれに続いていました。
火葬が終わり、炉から骨だけになって出てきた父を三つの骨壺に分けました。
我が家の墓は、東京の青山霊園と京都の東大谷墓地に分骨なので二つはその分として。後の一つは生前から父が妹の愛に頼んでいた骨をすりつぶした粉を粘土に混ぜて陶器を焼き兄弟に配るため持ち帰りました。
実は、私はこれに父の生前より反発しており「自分がこの世を去った時、残された子供たちが後の処理に困るから俺はいらない」と伝えていました。
「その代わり、その時は親父の骨を食らうよ」とも伝えていました。
口内を火傷するほど熱くないか骨に触れて確認した後、ふた欠片ほど口にほうばり、それを力強く嚙み砕き咀嚼しました。
すると愚道も、あと弟や妹の何人かも父の骨を口にしました。
味のない炒り粉のようでした。
異様な光景かも知れませんが、奇人の父に育てられた子供としては、そんな事は驚くほどの事ではありません。
火葬場の職員さんがドン引きしていたのは言うまでもありません。
これで完全に大愚花房東洋の肉体は無くなりました。
信念を持ち、ひとつの事を生涯通して貫いた姿は息子の私から見ても素晴らしく尊敬するばかりです。
なぜか人を惹きつける魅力的な人物でした。
台風の目のように、まわりを巻き込んで振り回す所にはいつも閉口していました。
急に思いついたらどんどん話を進めて、相手の都合なんてお構いなしでした。
色々あったけど、男としても、父としても私にとって最悪で最高の親父でした。
長い間お疲れ様でした。
合掌
(『維新と興亜』令和七年四月号)